「太平洋を泳いでアメリカまで行けるのか?」そんなバカげた疑問に、実は過去に真面目に挑戦した人物がいる。
夢物語のように聞こえるこのチャレンジ、果たして現実的に可能なのか?物理的条件、前例、リスク、必要なサポートなどをもとに、冷静かつ正確に検証してみよう。
太平洋横断、その距離と条件を知っているか?
──銚子からサンフランシスコまで約8,700kmという非常識
太平洋を「泳いで」横断する、という発想は正直どこかファンタジーだ。だが、現実にそれを試みた人がいる以上、まずはこの挑戦がどういうスケールなのかを整理しておく必要がある。
出発点は日本・千葉県銚子市、ゴールはアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコ。直線距離でおよそ8,700km。ちなみに、東京からニューヨークの直線距離は約10,887km。
それよりは短いが、泳ぎで超えるには桁違いのスケールだ。飛行機なら10時間、船でも数週間。それを人間が「泳ぎ」でカバーしようなんて、もはや距離感覚が破綻していると言わざるを得ない。
さらに、太平洋はただ広いだけじゃない。海流、風、天候、そして気温変化が容赦なく襲いかかる。波は荒れ、時には熱帯低気圧が進路をふさぎ、日差しは肌を焼き、夜は体温を奪っていく。
そして当然、そこは野生の海。サメやクラゲといった生き物も、泳ぐ人間にとっては立派なリスクだ。
「泳げる距離じゃない」という常識は、決して誇張じゃない。現実として、太平洋横断は人力で片付くスケールをはるかに超えている。
それでも、挑戦した人がいるのはなぜか?次の章ではその実例に迫る。
実際に泳いだ人がいた:ベノワ・ルコントの挑戦
──2018年、日本からの出発と記録された2,800kmの真実
「太平洋を泳いで横断したい」なんて、本気で言い出したら普通は病院送りだ。でもその“正気とは思えない”挑戦を、実際にやってのけた男がいる。
名前はベノワ・ルコント(Benoît Lecomte)。フランス生まれ、アメリカ在住の長距離スイマー。2018年、彼は日本の銚子からカリフォルニア・サンフランシスコを目指して、泳いで太平洋を渡るというプロジェクトを始めた。
その名も「The Longest Swim」。うん、名は体を表してる。
で、どうなったかというと——完泳はできなかった。
実際に泳いだ距離は約2,800km(1,753マイル)。これは決して失敗とは言えない。1日8時間、何ヶ月も泳ぎ続けた末の記録だ。けど、支援船のメインセイルが壊れたり、天候が荒れまくったりして、彼はハワイの手前で中断を余儀なくされた。
しかもこの挑戦、完全に“泳ぎっぱなし”じゃない。ルコントは支援船とともに行動し、泳ぐ → 休む → また泳ぐ、を繰り返して進んでいった。場所はGPSで記録し、再開する時は必ず同じ地点から。
いわば「分割式横断」。それでも、海のど真ん中で何百時間も泳ぐって、普通に正気の沙汰じゃない。
彼の挑戦は、ただの冒険じゃなくて海洋環境への意識啓発も兼ねてた。海洋プラスチック問題や放射性廃棄物の調査をしながらのスイムだったっていうから、もう変態の中でも超実用派ってやつだ。
ナイス。じゃあそのまま流れに乗って、第3セクションいくよ。ここでは「泳ぎっぱなしは無理」っていう現実をぶつけて、分割スイム+支援体制の話を掘り下げる。夢に水を差すってより、現実って案外キツいよね、って話。
泳ぎっぱなしは無理:サポート船と分割スイムの現実
──単独横断ではなく「伴走+休息+GPS記録」という方式
「太平洋を泳ぐ」って聞いたとき、多くの人が想像するのは“波間をひたすらクロールで突き進む人影”かもしれない。
でもそれ、完全にファンタジー。現実はそんなロマンチックじゃないし、むしろガチの現実主義者しか生き残れない世界だ。
まず、泳ぎ続けることは不可能。身体は当然休息を必要とするし、栄養も睡眠も水分もないと、数日もたずに沈む。ルコントの挑戦を支えたのは、常に伴走する支援船だった。寝るのも食べるのもそこで、天候が荒れれば一時停止。再開するときは、GPSで記録した“最後に泳ぎ終わった地点”から再スタート。
つまり、「連続ではないけど、インチキでもない」という絶妙なバランスで成り立ってた。
この方法を“分割スイム”って呼ぶ。水泳でマラソンするようなもんで、長距離を少しずつ区切って泳ぎ、累計で横断距離に達する。どれだけ分割しようが、累積距離がリアルなスイムである限り、記録としては成立する。
でも、ここで勘違いしちゃいけないのは──
これ、決して楽なやり方じゃない。むしろ、しんどさの種類が違う。
たとえば、毎日8時間以上海水に浸かってると、肌はズタズタ。塩で擦れて傷だらけ、日焼けも皮膚炎も地獄。しかも、精神的にはずっと「終わらない泳ぎ」を繰り返すことになる。これはもう、スポーツというより修行に近い。
サポートがあるからって甘く見たら痛い目見る。むしろ、「泳ぐ」だけじゃ足りない。気象、航路管理、医療対応、物資調達…これ全部、裏で動くチームがいなきゃ成立しない。
つまり、「人間一人の力で太平洋を泳いで渡る」は成立しない。実際に渡ってるのは、“人類の集合知”だ。
想定される脅威:天候、海流、海洋生物、そして人間の限界
──サメだけでなく、嵐と塩分で普通に死ねる
太平洋って、たぶん人類が最もナメてはいけない海域のひとつだ。地図で見るとただの青い空間に見えるけど、実態は人間の生存を拒絶するフルコンボの詰め合わせパックみたいなもの。
まず天候。これはもう最大のラスボス。嵐、熱帯低気圧、突風、急変する気温…どれも命に直結する。支援船があっても、荒天が数日続けばスイムは強制中止。
しかも気象衛星のデータを毎日チェックしないと、ルート全体が吹き飛ぶレベルの事態も起こり得る。
次に海流と潮の流れ。ルコントもそうだったけど、泳ぎの大半は「海と喧嘩」してる時間。向かい潮に当たれば時速1〜2kmの進行すらままならないし、逆に流されれば数時間の努力がすべて無に帰す。
海は「頑張ったから報われる」みたいな人間社会のルールを一切守ってくれない。
そして海洋生物。みんな大好き、サメ。もちろん、出る。ルコントも何度も遭遇してる。でも本当に厄介なのは、クラゲや小型生物の刺胞。目に見えないレベルの触手で皮膚がかぶれ、やけどみたいなダメージを受けることも。
ちなみに、夜は発光プランクトンが幻想的らしいが、そんなロマン見てる余裕あると思う?
でも最大の敵は、結局のところ人間の身体そのものだ。
数日間の連続スイムで肌は海水焼け、関節は腫れ、脱水、低体温、慢性的な疲労と孤独。体だけじゃなく、精神も削れていく。毎日「まだあと7,000km」って現実を突きつけられるって、もうそれ拷問でしょ。
「泳げれば行けるんでしょ?」という発想は、ゲーム脳にも程がある。太平洋は、舐めた人間を何度も海底に沈めてきた。
だからこそ、挑戦するなら──覚悟ごと、自分を海に放り込め。
理論上は可能、でも現実は“人類規模のチャレンジ”
──成功の鍵は「泳力」より「支援体制」にあり
ここまで見てきたように、太平洋を泳いで渡るのは不可能じゃない。いや、“理論上”は可能だ。
それはベノワ・ルコントが実際に2,800kmを泳いだという事実が証明している。GPSで管理されたルート、分割スイムという形式、支援船の存在。これらがあれば、少しずつ距離を積み上げていくことはできる。可能性はゼロじゃない。
でも、そこに必要なのは“泳力”だけじゃない。むしろ泳ぎそのものは全体の5割にも満たないかもしれない。必要なのは、
- 気象や海流を読むナビゲーター
- 船の運航を管理する専門スタッフ
- 医療と栄養を支えるチーム
- 継続的な資金とサポーター
- そして、数ヶ月にわたって孤独と疲労に耐える鋼のメンタル
つまり、これはもう個人のチャレンジというより“プロジェクト”だ。企業レベルの組織力が必要で、精神的には宇宙飛行士、肉体的にはアイアンマン、しかも長期間結果が出なくても腐らないような“狂気と理性の同居”が求められる。
要するに、「泳げば渡れる」なんて甘い話じゃない。“自分一人で泳ぎ切る”なんて発想は捨てたほうがいい。
むしろ、自分がそのチームの一員になれるかどうかを考えるほうが現実的。だってこれは、個人で立ち向かうにはあまりに大きすぎる挑戦だから。
太平洋を泳いで渡る。
その言葉の裏には、人類が積み重ねてきた知識と技術と、そして狂気が詰まってる。
ロマンがある?
もちろん。
だが、そのロマンを現実に変えるには、“夢想家”ではなく“現実主義者の皮を被った変人”が必要なんだ。
まとめ
太平洋を泳いでアメリカまで渡る。それは一見、酔狂な夢物語のように見える。だが実際に挑戦した人がいて、数千キロを泳ぎ切ったという事実がある以上、「理論上は可能」は確かに本当だ。
ただしそれは、支援体制・計画・精神力すべてを極限まで整えた場合の話。泳力だけでは太平洋は渡れない。人間ひとりの挑戦に見えて、その裏では人類の知恵と総力が問われている。
だからこそ、この挑戦はロマンではなく、現実に触れた人だけが語れる“覚悟の物語”なのだ。
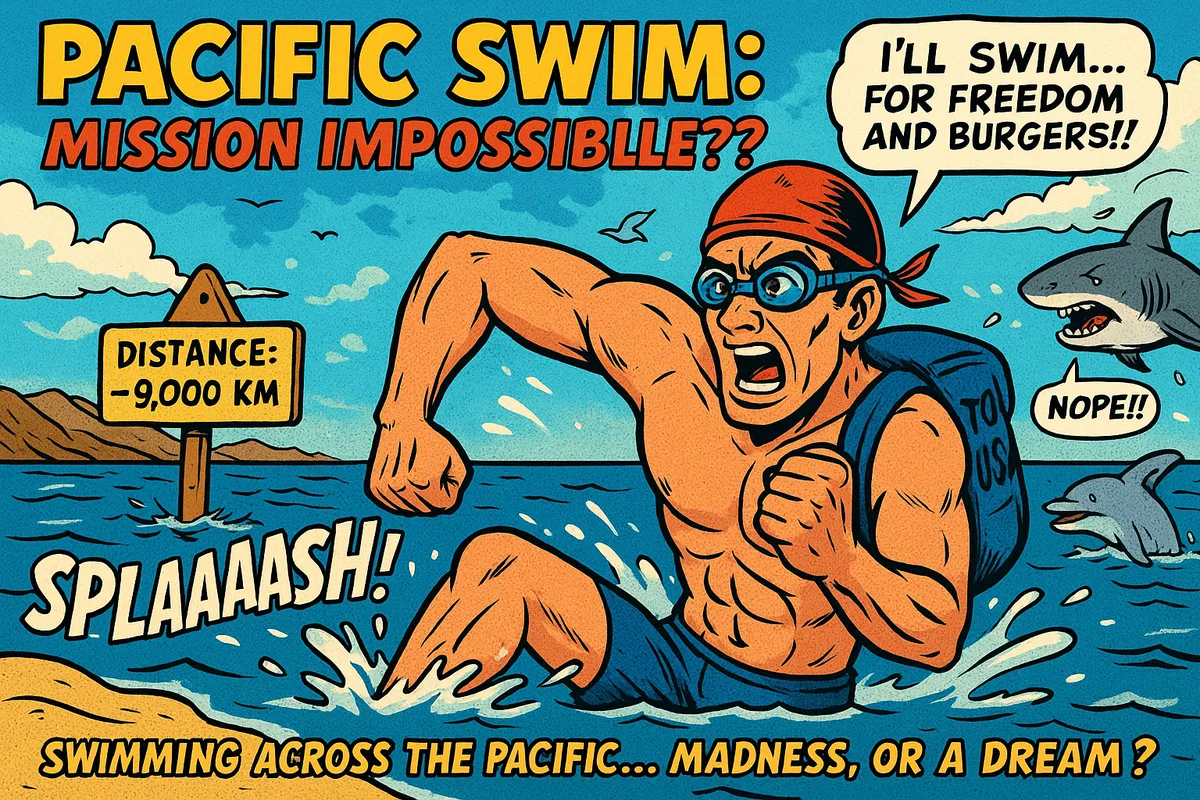
住民の声